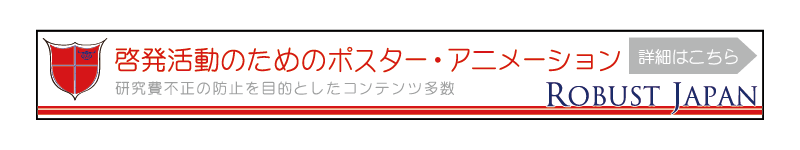申請書の作成に取り組まないといけないと頭ではわかっているものの、気持ちが重くなって手が止まってしまう人や、書くことに苦手意識を持ち、何をどう書けばいいのかわからないと感じる人は、具体的な手順が見えないために途中で挫折してしまうことが多いようです。
特に、申請書を書くのに慣れていない人は、文章テクニックを学ぶことから始めようとしがちです。しかし、文章の技術を習得するにはある程度の訓練が必要で、時間がかかるうえに途中で諦めてしまうことも少なくありません。効率的かつ最短で結果を出しながら申請書作成のスキルを向上させるには、学ぶべき順番を押さえることが重要です。
何をどの順番で学ぶべきか
科研費.comでは効率の良い順で学べるようにコンテンツを配置しており、少しの努力で大きな成果を出せるよう工夫しています。結果が出れば、継続して学ぶモチベーションも上がります。どうしても時間が限られている人には添削サービスも行っていますが、まずはご自分で学習してみてください。
1.何を研究するか(研究テーマとアイデアの生み出し方)
必要な時間 ★
得られる効果 ★★★
研究テーマそのものについて考えることのできる(実質、最初で最後の)チャンスです。良い研究はテーマから。ここでつまらないテーマを選んでしまうと以降で頑張ってもたかだか知れています。
2.申請書をどのように書くか(何をどこに書くか)
必要な時間 ★★
得られる効果 ★★★★
もっとも効果の高いところです。うまく書けない人のほとんどは、聞かれていることについて答えておらず、同じような内容を繰り返し書いています。聞かれていることだけに答えるのがポイントです。
3.どうすれば魅力的な申請書になるか(どう見せるのか)
必要な時間 ★★★★
得られる効果 ★★
最後の最後に+αを狙うにはピッタリです。内容面での推敲はほとんど必要ないので、残り時間が少ない直前での見直しにピッタリです。
どう学ぶか
理解した後は、ひたすら書くしかありません。何回か書くと、自分でも良く書けたなと感じる瞬間が出てくると思います。うまく書けたものについては他の申請でも使いまわしつつブラッシュアップしていきます。
何度も同じような文章を書いていく過程で自然と表現は洗練されますし、わかりにくいところ、自分で書いていてロジックがつながっておらず書きにくいところも明らかになっていきます。
そして少し間をおいて、また本サイトなど新しい知識も取り入れて、また書き直してのように書く→見直す→間を置く→書く…を繰り返すと良いでしょう。年に1度の科研費・学振シーズンだけしか申請書を書かないのであればうまく書けなくて当然です。年間を通じて募集がある民間財団や他の助成金にも出し続けることで申請書作成の能力が上がることはもちろん、研究費も獲得できます。